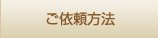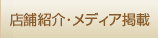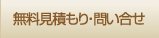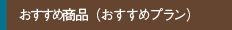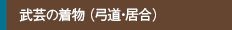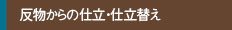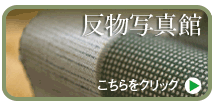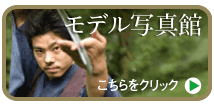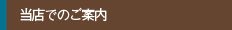| 用語 | 意味 |
| 湯のし | 反物を蒸気をあてて布巾を一定にし布目を揃えます。仕立前に湯のし機に通しての仕上げ加工です。 |
| 紋入れ・ 着物 湯通し |
織物では仕立前にお湯に通して糊や不純物を取り除きます。柔らかくしなやかになります。 |
| 筋けし | 仮縫いのきものを湯のしをして筋を消すこと、又は、裄出しの時元の仕立ての筋を消す事です。 |
| 地直し | 色補正と同じ意味です。しみなどの個所を色筆で色挿しして彩色補正する事です。 |
| スレ直し | 擦れて白っぽくなったのを「スレ」と言って生地の表面の繊維が切れた状態を言います。スレ直しである程度は直せます。 |
| やけ直し | きものの地色が日焼けで色が変わってしまう事がたまにあります。それを色刷毛して直す事です。 |
| 染色補正 | 地直しと同じ意味です。 |
| 紋抜き | 紋を入れ替える時、家紋を色を抜いて白くすることです。 |
| 縫紋 | 糸で縫って家紋を輪郭で表現します。縫い方がいろいろあります。略礼装でひとつつける時が多いです。 |
| 染抜き紋 | きものの地色から家紋のところを白く染め抜いて、輪郭を墨で書いたものです。 |
| 上絵 | 紋入れの事です。家紋は4,000から5,000種類あって、普通の紋は紋帖にのっています。 |
| 八掛 | 袷のきものの裏地で、「裾回し」とも言います。身頃八掛4枚、おくみ八掛2枚、袖口八掛2枚、衿先八掛2枚の合計10枚の布から成り立っています。 |
| 胴裏 | 袷物の胴の部分の裏地、普通は2丈必要です。 |
| アンサンブル | 物と羽織のお対(お揃い)の事です。大島のアンサンブルなんてよく聞きますね。 |
| 石持 | 「こくもち」と読みます。紋入れする為に反物の時に白く丸が抜けているものを言います。 |
| 堅牢度 | 「堅牢」(けんろう)とは強さの事です。きもの業界では「堅牢度」という表現です。 |
| お召 | 先染めのちりめんの事で先に糸を染めて横糸に撚りの強いお召糸を使って出来る織物です。 |
| 1丈 | 3メートル78cmと8mm??1尺の10倍 |
| 1尺 | 約37cmと8mmの1寸の10倍 |
| 1寸 | 約3cm 7mm |
| 1疋 | きものの2枚分が反物になっている状態の事。 1反約12メートルの2倍 |